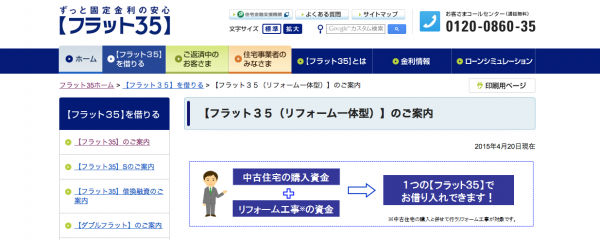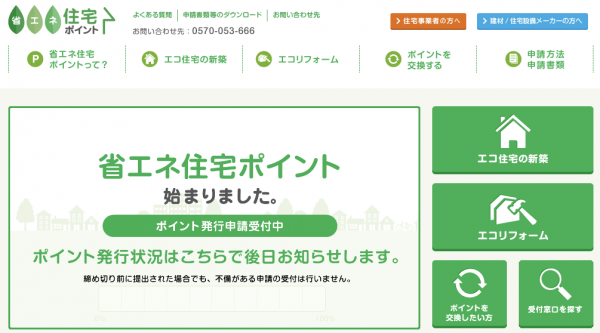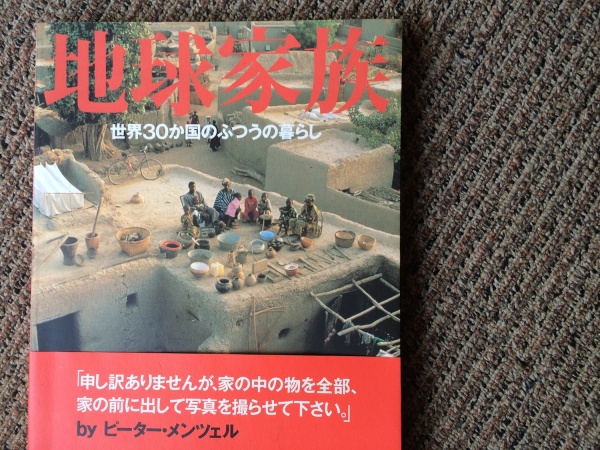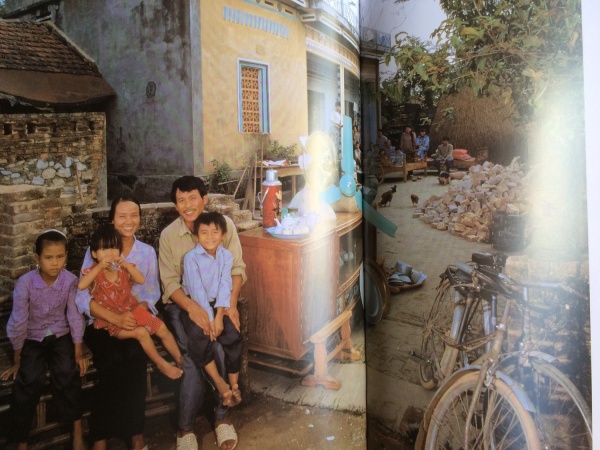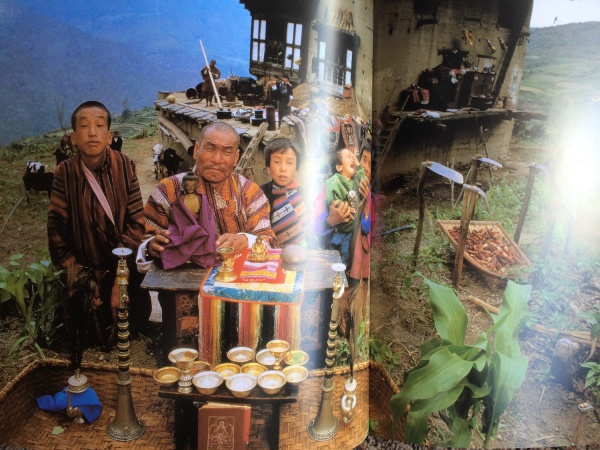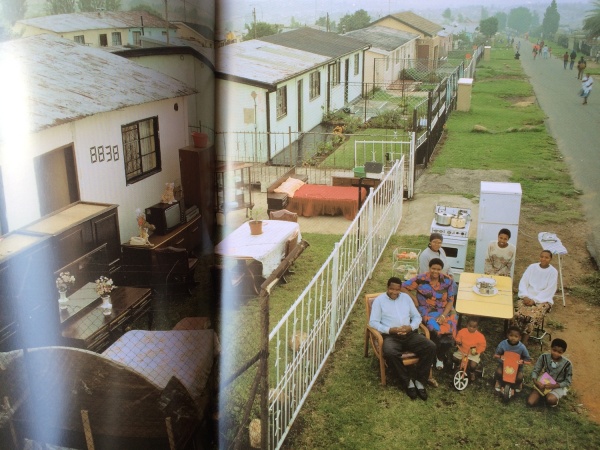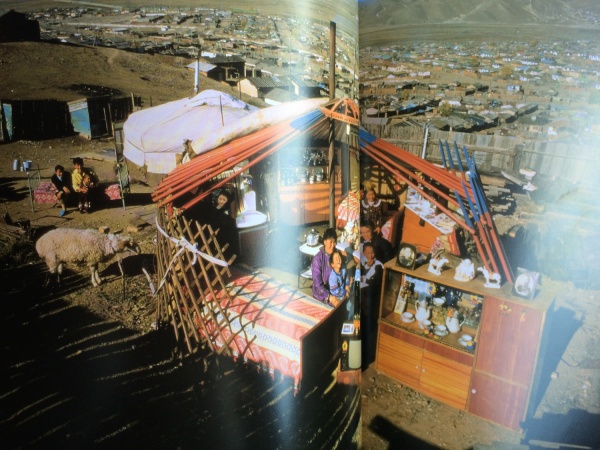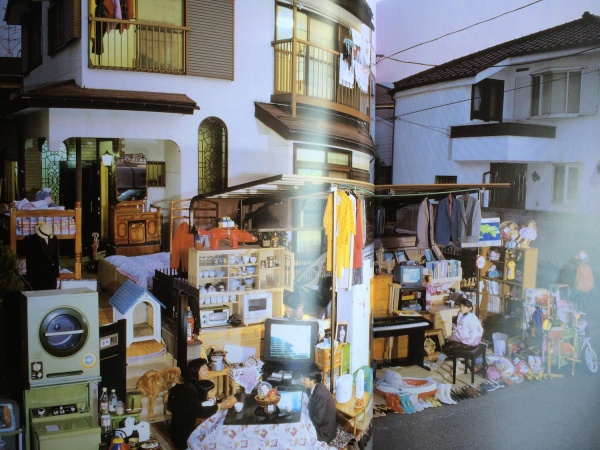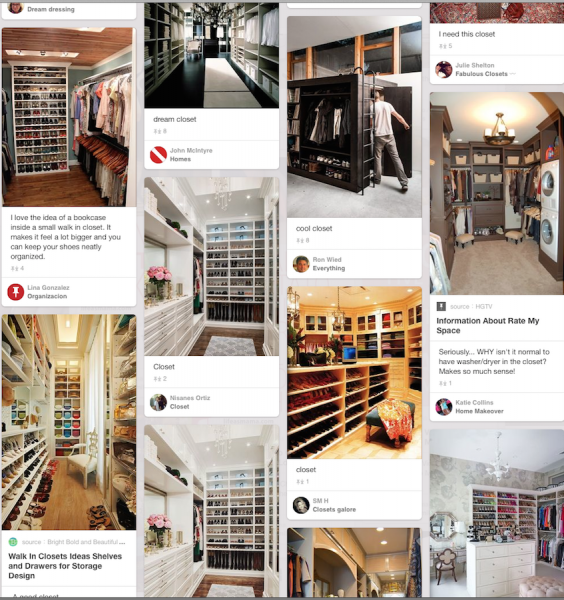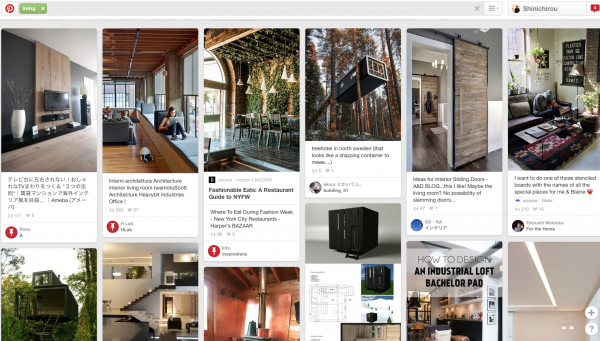2015/02/23
築50年の平屋戸建て賃貸にて暮らしの実証実験。先日からなんどか記事書いてきましたが、今日はその住宅をリフォームした際、窓周りをどう納めていたかを書いてみます。今回の内容はどちらかというと玄人向けに書いていますので、一般の方には分かりにくい表現あるかもしれません。その時はググってみるか、ぼくに聞いてみてください。
◎大げさに触らない。
築50年の住宅をリフォームして使うといっても、テレビでおなじみのような大掛かりな工事はやりません。というかできませんよね、賃貸なんだから。ただそれでも、少しでも快適に、そして気持よく暮らしたいもの。そこで、今回のリフォーム内容は大きく3つだけにしぼりました。もちろん大家さんへの相談確認、無事OK頂きました。
①床材の無垢化。
②内装塗り壁の色変更。
③開口周りの補強と装飾。
◎なるべくゴミを出さないように。
まずは床の無垢化。不動産屋さんの案内でこの住宅を訪れたとき、床材はいわゆる合板系の薄っぺらいフローリングでした。それでもワックスが掛けてあり、ぴっかぴかに光ってました。

合板系フローリングと既存の状態。
賃貸によくある、退去時のリフォームです。とにかく新しいものに交換、そしてなるべく安くというものです。これをなんとかしたいということで、いつも使っている杉の厚板30mmに交換。と思いましたが、張り替えとなると、今張ってあるフローリングを剥ぐ必要がありますし、その後ゴミとして処分しなければなりません。
もちろん剥ぐにも、ゴミ捨てるにもお金が掛かるので、張り替えをやめ、杉板を8mmくらいに加工してもらい、現在のフローリングに増張りすることを選択。敷居とか、扉の下端とかの調整はありましたが、見事狙い通りに増張りできました。
たたみ敷きの2部屋はたたみを処分して、ここには杉の厚板30mmを張りました。あらためて踏み比べると、厚板の方がやぱり気持いいですね、当然といえば当然です。ゴミの量を減らす、手間を減らす意味ではこの増張りはいい方法でした。
◎色は重要な環境要素です。
人それぞれに好きな色、嫌いな色あると思います。色を決めるとき、折角塗り替えるならちょっとポイントでとか、テレビや雑誌のようにかっこ良くと、濃い色を選ばれることよく見てきました。おしゃれなショップや、飲食店でも濃い色が使われているところ多いです。いいなぁと思われる方も多いと思いますが、濃い色はきちんと考えて塗らないと失敗します。
なにが失敗になるかというと明るさです。濃い色は光を吸収してしまい、同じ明るさにも関わらず暗く感じてしまいます。反対に白い色は光を反射し、少ない明かりでも明るく感じさせてくれます。

壁塗りは家族で楽しめます。
好きとか嫌いとか、かっこいいとかかっこわるいとかの感覚とは別に、明るさの違いを感じるのには、色が薄い濃いというのが影響するということです。そういうことなので、もちろん真っ白に塗り替えました。夜の照明のあかりはもちろん、曇りや雨の日でも明るく光を反射しています。
◎簡単で効果的、開口部の補強。
そして今回のリフォームの目玉、地味ですけど開口部の補強です。今あった開口部はさすがに築50年、なかなか大胆な隙間と、ペラッペラなガラスに、これまたぺらぺらなアルミ枠。断熱なんて全く期待できないものでした。よくも前の人はこの状態で暮らせたなと変な関心をしました。
サッシの上にはカーテンレールがセットされています。ここにカーテンが下げてあったのでしょう。カーテンが好きじゃないという人はだいたいここでブラインドとか、ロールスクリーンを選ぶんですが、うちの場合はやっぱり紙障子です。普段から使っているので、その性能や雰囲気も一番分かっています。
ただ、障子を取り付けるにはそれらを走らせる敷居や鴨居、それにタテ枠(方立て)が必要です。それらをどう納めるかで、性能にも見た目にも大きく影響してきます。今回のリフォームでは、既存サッシとの取り合いに注視して枠材を加工し、現場に取り付けました。
◎既存サッシと枠の取り合い。

既存の押し入れ枠との取り合い。
右手に見えるのが今回追加した障子と障子枠です。その上にアルミサッシが見えますが、欄間付きのサッシでした。この部分は天井に近い部分なので、冬場のダウンドラフトは気にせず、夏場に解放できるようにあえて障子は設けませんでした。
思った通り、冬場は問題なかったです。で、左手に見えるのが既存の押し入れ。障子枠がついた分、押し入れのふすまは最後までしまっていません。ただ、見た目には引き違いなのであまり分かりません。時代のついた押し入れ枠と、真新しい障子枠のコントラストがリフォームならでは。

押し入れ内部から。
押し入れの内部からの様子です。写真中央の入隅に縦に見えているのが、元々の押し入れタテ枠です。その手前が化粧で張ったラワンベニアで、その手前が新規の押し入れタテ枠です。だいたい130mmほど押し入れの出し入れ範囲は狭くなったのですが布団の出し入れには問題なしです。

障子枠の足下、敷居の様子。
ここの床が既存フローリングに増張りしたところです。なので、敷居も床の上に乗っかっています。掃き出し窓といいますが、現代では外に箒で掃くことなんて無いのでこの段差は問題なしです。外部にデッキなどがあり室内と繋がる場合には床にあわせた方がいいかもしれません。あるいは、腰掛けれるくらい高くしても面白いですね。

押し入れ枠と掃除枠の関係。
押し入れ、障子共に開け放った状態です。大工さんの気持ちが伝わってきます。右手サッシの上部入隅には隙間が見えます。クレセント掛けた状態でこの有様。障子なしではダウンドラフト以前にすきま風がすごかったはずです。

ふすまと障子。
障子枠分だけ、ふすまのタテ枠の位置がずれてます。こんなところにドキッとするのはマニア過ぎますか(笑)。

間仕切りふすま戸と障子。
こちらは、部屋の間仕切りになるふすま戸(写真中央)と隣り合った部屋の障子窓の様子です。

サッシ現しの状態。
この三方からふすまや障子が取り付く枠。実は内部は空洞になっていて、3枚の枠材がくみ合わさって柱状に見えているだけです。取り合いの出隅部分をピン角で納めないのは、ぼくのただのこだわりです。留が好きな人は留でもいいと思います。

鴨居の状態。
既存の鴨居にしっかりタテ枠が取り付いています。

玄関ドア。
こちらは番外編。玄関ドアです。廻りのタイルの雰囲気、縁取られたアルミの部分を見てもらうと分かる通り、The60’sといったニオイがぷんぷんします。もともとついていた扉もそんな雰囲気だったので、それもいいかなと思いましたが、やっぱり建て付けが悪くなっていたので、スギの板戸に交換しました。
で、いつか試してみたかった荒材での仕上げに挑戦。毛羽立った板の雰囲気が何ともやさしい。変化を楽しむために塗装もしていません。どんな風に成長するか楽しみです。

見えるかな?
もうちょっと寄れば良かったのですが、板材の毛羽立ち見えますか?もうちょっと荒々しく毛羽立っていても良かったのですが、建具屋さんが遠慮して磨いてくれてました。築50年のペラペラアルミ枠を残して、扉だけを差し替える今回の方法も十分使えるやり方でした。既存枠に、ビス穴とか傷とかは残りますが、それすら愛おしくなります。
◎やっぱり面白いリフォームは。
いかがでしたか、自宅のリフォームの開口部廻りに特化して書いてみました。本来であれば断熱改修も含めてやれればなお良かったのですが、さすがにそこまでは賃貸に投資できませんでした。これが持ち家のリフォームであれば、ものすごく快適な健康住宅に生まれ変わっていたでしょう。たった、紙障子を追加しただけでこれだけ暖かくなったのですから。いやーほんとリフォームって面白い、大げさなものでなくても、アイデアと暮らし方の工夫で楽しさ倍増になるんです。