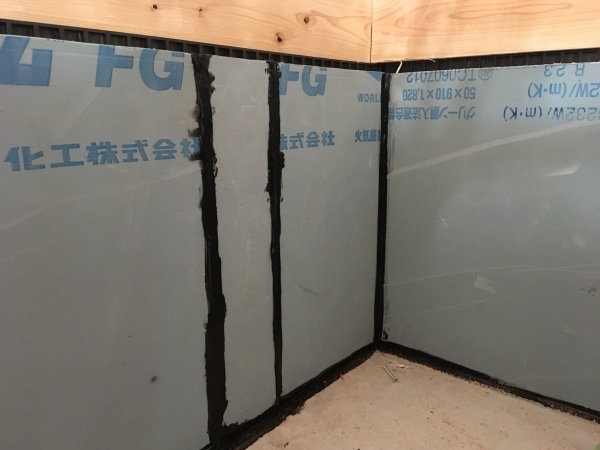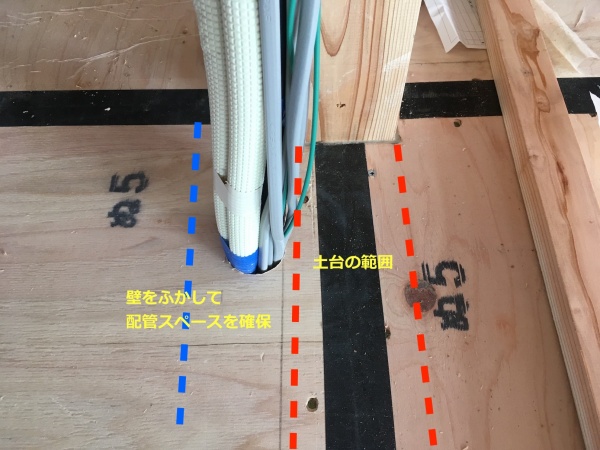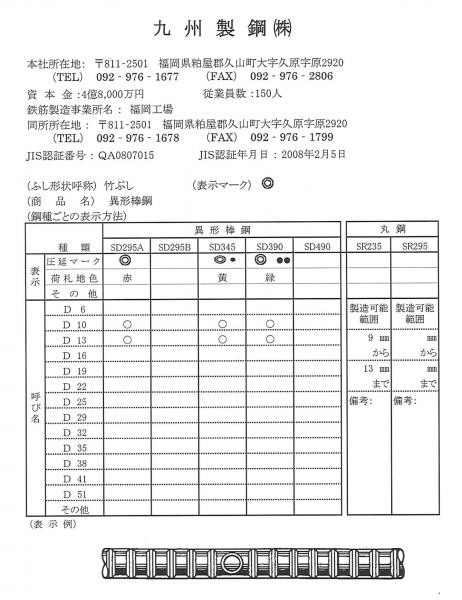堰堤(えんてい)に魅せられてダム巡り!
2019/02/28
始まりはヘリテージマネージャー
こんにちは、久しぶりにプライベートなネタにてブログ書いてみます。先週の日曜日福岡県うきは市へ「ダムを訪ねるドライブ」へ行ってきました。ダムっていきなりどうした?ってツッコミは家族からもう十分いただいておりますのでこちらではご容赦ください。とはいえ、なんでダムなの?の答えは、ダムの魅力に取り憑かれたから。そのきっかけとなったのが、全国の建築士会(建築士が個人として登録する社団法人)が開いているヘリテージマネージャー養成講座を受講したこと。全14回(1回約4時間)約半年間、毎週土曜日の午後はみっちりこの講座に出席していました。その内容は建築士として、地域に埋もれている歴史的価値を軸に、残しておくべきものを探し出し、その存続のためのアイデアや、保存修理の監修、文化財への登録支援などなど。そんなヘリテージマネージャー養成講座の最後の課題が「私が見つけた登録文化財」というものでした。

僕が選んだのはこの施設。菊池川第五発電所、菊池渓谷へ登っていく途中にある九州電力の水力発電所でした。秋の行楽シーズンに渓谷へ行った時、近くの駐車場がいっぱいで随分下の駐車場に停めさせられて、家族にブツブツ言われながら歩いていて見つけた施設です。見つけた時はぞくっとしましたよ。

その施設の中で文化財として押したかったのがこの部分、水力発電に必要な水を一定方向へ導くための堰(せき)。湾曲した美しいフォルムです、しかも石で作られています。施設には近づけないのでよく見えませんが、おそらく自然石です(ひょっとしたら間地石とか割り石?)。

現地看板の情報によると大正12年(1923年)に完成とあります。96年前の施設でしかも現役。建物やその内部の発電装置などは繰り返し更新されているようですが、この堰はきっと当時のまま。すごい難工事だったと看板にありました。重機などない時代に、岩盤を掘り進み場所を確保し、石を地道に積み上げた当時の光景を思い浮かべると、じーんときました。これが堰堤マニアの始まりなのでした。こんなのが他にもいっぱいあるんじゃ?と思うと、見に行きたくなるじゃないですか。

ということで、現地看板にあった菊池川第一発電所、(第五発電所より下流なのに第一発電所)まで行ってみました。やっぱり石積みの堰があります。曲線は第五発電所には敵いませんが、苔むした感じはいいですね。奥にある施設もその風化感が哀愁放っていてGOODです!

調子の乗って、他にもないかなとキョロついているとこんな石橋に遭遇。道路からは全く見えない場所です。本道路から狭い道路へ降りて行ってみると、どこかで見たような・・・。なんと、大河ドラマいだてんのロケで使われたところでした。そんな案内板なかったのですが、絶対そうです。奥に見える建物もドラマでは藁葺きでしたが、そんなのセットで作れるだろうし。あとで調べみたらやっぱりそうでした。県指定文化財である永山橋(明治11年築造)、文化財つながりでの発見にまたもや身震い。一人でカメラ持ってウロウロ、なかなか怪しかったかもしれません。
堰について調べてみると・・・
こんな感じで堰に興味が湧きだし、検索してみるとあるんですねやっぱりいろいろと。マニアの方もいっぱいいらっしゃるようです。そこで出てきた情報が「ダムカード」というもの。ダムカードって何?トレカみたいなものなのかと想像はつきましたが、そんなものがあるのか、にわかに信じられず、さらに調べてみるとまたまたグッドな情報が現れました。天皇陛下御在位三十年を記念して、特殊デザインの記念ダムカードを配布いたします。 ← 国交省へのリンク
こんな報道が国交省から出ているではありませんか。どこでもらえるのか見てみると、いろんなダムで無料で配られているとのこと。こりゃもらいに行かねばということになったわけです。ただ、対象ダムの数が多くて九州だけでも93カ所あります。的を絞らなければならないので、まずは見た目ということで石積みをキーワードに。

福岡県うきは市にある藤波ダム。石積みを基本としたダムのことを「ロックフィル方式」と呼ぶこともわかりました。かっこいいです!

さすがに手作業ではないでしょうが、石積みです。洪水抑制の治水ダム、右側が水上で左が水下になります。

ボリュームはこんな感じ、スケールでかいです。

水上側にある排水溝、高さ30mくらいあります。大雨などでダム湖の水が増えた時、ここから下流側へ流されるとのこと。想像しただけでゾッとしますが、放流を見てみたい気もします。

その下流側です。とてつもないデカさの水流コースターです。

下流側からその滑り台をみると、上から見るよりゾッとしました。写真でわかりにくいですが、高さのスケールに圧倒されてしまいます。入っちゃいけないところだったっていうのもあるのですが・・・(汗。
家内と娘は車で退屈そうに待っていたので、ダムカードの申込書をいただいて、藤波ダムをあとにしました
せっかくきたので付近を探検
ここまできたので他にもないかとgoogleマップを見てみると、近くにもう一つダムがありました。合所ダムです、行ってみるとこちらも迫力満点。ただ付近の道路からでは近づけなかったので、別の角度を狙って・・・。
下流側へ来てみたのですが肝心のダムが見えない。ただ、むき出し鉄骨が錆び朽ちている廃墟と、そこへ繋がるコンクリート製の橋、さらに奥には鉄骨製の橋、そして綺麗な川という、いい感じのロケーションに出会えたので良しとします。肝心な合所ダムへは同伴者の退屈がピークに来ていたので次回にということになりました、残念!

帰り道の出会い。バス停ですがシュールなミニオンに囲まれて。ちょっと機嫌が良くなりました!

さらに寄り道ということで、魚返りの滝に行って

斧渕の滝を覗いて・・・もうだいぶ日が傾いて来たのでいよいよ帰ろうと山を下っていると・・・

ダムを発見!砂防ダムですね。しかし、見慣れた砂防ダムではなく、鉄管が設置されています。「鋼製フレーム堰堤」というそうです。流木や巨石はここで引っ掛けて、水は流すというものでしょう。ダムにもいろんな役目がありますね。さらにダム(堰堤)に興味湧きました。自転車で堰堤巡りとか、これからの季節気持ち良さそうです。ちょっと計画してみますかね。

こちらは藤波ダムへ向かってる時に途中立ち寄った「石積みの棚田」、農閑期だったのでちょっと寂しかったですが、シーズンであれば石積みと緑のコントラストが綺麗なのは想像できますね。偶然でしたが、やっぱりこちらも石繋がりでした。
今回の堰堤巡り、ほぼ思いつきで行ったのですが、なかなか奥深いものがありました。今年は49歳にになります。設計の仕事で独立して今年で19年、来年はいよいよ20年の大台に乗っていきます。とはいえ、まだまだ先は長い。人生80年時代ももう古い、100歳まで生きるとしてあと50年あります。
仕事は生涯やっていきたいですが、仕事以外の余白も考えていこう。そう思っていた時だったので、この堰堤巡りはちょうど良さそうです。しかも自転車で廻れればと画策しています。自転車とカメラとスケッチブックなんかを持って、週末はサイクリング。想像しただけでワクワクします。こんな余暇が過ごせるよう、精神的にも体力的にも健康であれるようがんばろうと思います。あと50年も人生があるってあらためてすごいなぁと感じた旅でした。
なんでも結構です!ご質問などございましたら、ご遠慮なくこちらからお問合わせください。心をこめてお応えさせていただきます^v^。
”最後まで読んでいただいてありがとうございます。ついでにfacebookのいいねや、twitterでシェアいただけると僕は大変喜こびますので、あとひと押し、何卒よろしくお願いいたします。”